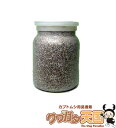冬のクワガタ幼虫採集・飼育方法 公園にて!
この記事はこんな方々へ最適です!
- 夏しかクワガタ採れないと思っている
- お子さんからクワガタ飼いたい!と言われた
- クワガタをどうやって採ったら良いか分からない
- せっかく飼うならクワガタ幼虫から飼いたい
- 都会ではクワガタ採れないと思っている
そんな方々のためにこの記事を捧げます。
そうです。
冬でもクワガタは採れます!
さらに、冬でもクワガタ幼虫は採れます!
本記事では主に『冬のクワガタ幼虫採集方法・飼育方法』について書きます。
この記事を読めば季節を問わず、日本全国どこにお住まいでも今すぐ採集に行ってクワガタ幼虫を採集できます!
本記事での「クワガタ」は主に「コクワガタ」「ノコギリクワガタ」「ヒラタクワガタ」を想定しています。
*カブトムシ幼虫採集はこちら↓をご参考ください。場所の見つけ方など共通点も多いです。
*オオクワガタを採集したい方はこちらをご参考に。
目次
クワガタ幼虫を採ろう!採れる公園の見つけ方
誰でも超低難易度で採集できるよう、本記事では採集地を「公園」とします。
日本全国、クワガタがいる公園は絶対1時間圏内にはあります。
なぜそう断言するかと言うと、私が大都会の東京23区内でも採集したことがあるからです。公園、バカにできませんよ!
自然がない東京23区でも、公園ではクワガタが採れるんです。ということは自動的にクワガタ幼虫も採れます。
皆さんのお住まいの地域でも、絶対に採れます。ご安心ください。
採れないのは単に知識がないだけ。本記事を読めばその知識が付きます。
公園の探し方①夏にクワガタがいる公園
これはカブトムシ幼虫採集も全く同じ話です。
夏にクワガタが採れると言われる場所なら、冬にはクワガタ幼虫が採れます。
東京で言えば、例として光が丘公園、石神井公園、林試の森公園、小金井公園、大泉中央公園などなど。
埼玉南部で言えば、秋ヶ瀬公園、川口自然公園、見沼自然公園、水子貝塚公園、三芳町緑地公園などなど。
お子さんがいる方は、子供のネットワークも最大限活用ください。
お友達はどこかで採集していないでしょうか?周りに聞いてみればヒントが出てきます。
ベテランの保育園、幼稚園の先生も頼りになります。我が家もポイント教えてもらったことあります。
公園の探し方②グーグルアース!ストリートビュー!
引っ越してきたばかり、お出かけ先の近くで探したい、土地勘がない、夏場の情報がない場合はグーグルアース、ストリートビューが頼りになります!
ご近所で下の写真のような雑木林を探してください。
1本2本の木じゃダメですよ。「雑木林」と言えるレベルでないとダメです。
以下は我が家が実際にクワガタ幼虫を採集した公園のグーグルアース写真です。
参考にしてみてください。


冬に葉の落ちない針葉樹(マツ、スギなど)の雑木林ではダメなんですが、グーグルアースからだと何葉樹か分かりません。狙うはクヌギ、コナラなどの広葉樹林です。
冬に落葉しているなら広葉樹、クワガタ幼虫がいる可能性あります。
グーグルアースは冬の写真とは限らないので、見分けつかなければ行ってみるしかありません。
ダメだったら公園で遊んで、また次の公園へ!にしましょう。
クワガタ幼虫は飛んで行きませんから次回で全然大丈夫です。
公園の探し方③検索!
あとは検索です。
例えば「さいたま クワガタ 公園」で検索すればたくさん引っ掛かりますよ。試してみてください。
(私のブログ記事もたくさん出てきますw)
私の実家のある東北地方の県名でも引っ掛かりましたが、もしかすると地方によりうまく行かない場合もあると思います。
人口が多いほうがネット記事も多くなりますので。。。
しかし県名、市名、公園名などと組み合わせて検索すれば、何かが引っ掛かるはず!
クワガタ幼虫を採ろう!公園の中の生育スポット見つけ方
クワガタが生息している公園の当たりをつけたら、さっそく出掛けましょう!
しかし公園は広いですよね。くまなく探すのは不可能。
公園の中である程度当たりをつけないと、時間がいくらあっても足りません。
ということでここからは当たりの付け方を解説します!
まずお伝えしたいのは、クワガタ幼虫は土の中にはいません。朽ち木の中にいます。
切り株、倒木、朽ち木を片付けてしまう公園はくぬぎ林があってもダメです。都立公園は、かつて落ち葉や倒木は掃除していたそうです。自然の昆虫がいなくなってしまったので撤去しない方針に変えたら、見事復活したとか。
そしてどんな朽ち木の中にいるかがポイントです。
湿気があり、しばらく時間が経った、固くない朽ち木
カラカラに乾いた雑木林にはクワガタは住めません。
落ち葉を掃除して綺麗にしているような環境ではダメ、乾きすぎます。湿気が大事です。
以下に写真を載せていますが、光の当たり方も是非ご参考に。直射日光ガンガンの場所では乾きすぎてクワガタ幼虫育ちません。
そして倒れたばかりの倒木・切り株ではダメです。
しばらく時間が経っているような、程よく朽ちたクヌギ、コナラなどの広葉樹の倒木、切り株、立ち枯れがポイントです。


このような立ち枯れにもクワガタ幼虫は入っています。

時間が経っていそうでも、叩いてカチカチの木はまだ若いです。
「朽ち木」にしかクワガタは産卵しません。
ある程度簡単に崩れなければその木はあきらめたほうが良いです。



どこの朽ち木かによって、いるクワガタ幼虫は変わります
地表の倒木、朽ち木にはほぼ「コクワガタ」しかいないと思ってください。
「ノコギリクワガタ」「ヒラタクワガタ」の幼虫は、朽ちた切り株、立ち枯れの土中部分にいます。
こちら写真分かりづらいのですが、切り株の根の部分を掘っていって、太い根の中にいたノコギリクワガタの幼虫です。

クワガタなら何でも、という場合は地表の材でコクワガタ幼虫を狙うのが簡単です。
ノコギリクワガタ、ヒラタクワガタはスコップで土堀り必須ですので、難易度上がります。私もそうでしたが、コクワガタが採れると他のクワガタ狙いたくなるんですよね~
採りすぎ・割りすぎ厳禁!
材割採集は、極端に言えばクワガタ幼虫の住処を破壊することです。
あなたが破壊しなければ、来年クワガタ成虫メスが産卵できたかもしれない。
また、木が朽ちるには時間がかかります。あなたが今日割ってしまうと、同じ朽ち木ができるまで数年の時間がかかります。
材割でのクワガタ幼虫採集は、このような犠牲のもとに成り立っています。
絶対に、自分が飼いきれない数量を採集しないでください。節度を持って採集お願い致します。
また、あまりにも強い力で材を割ると幼虫も殺してしまうことがあります。
そ~っと材割するようにしてくださいね!
クワガタ幼虫採集に必要な道具
素手でも採れるカブトムシ幼虫と違って、クワガタ幼虫採集は道具が必須です。
ですがご安心無用です。ほぼ100均で揃います。
おすすめは千枚通しとスクレイパーですね。
それがあれば朽ち木を割ることできると思います。
ご参考までに100均昆虫採集用品の紹介です。
あとは、採集した幼虫を入れる一時保管のケースやプリンカップをお忘れなく。
このような空気穴を開けたフタつきケースに、後述する幼虫用マットを入れておけば良いです。

もしノコギリクワガタやヒラタクワガタ幼虫を探すんだ!ということでしたらショベル必須です。
折りたたみショベルでしたら、電車、バスでの採集時も便利です。
私はこれをリュックに入れて採集に出かけています。
幼虫を採集したら: 幼虫飼育方法
個別飼育は必須
カブトムシ幼虫はまとめ飼いOKです。ひとつのケースに狭すぎなければ複数頭入れられます。
クワガタ幼虫は複数頭飼育はNGとされています。
クワガタ幼虫を飼育して見ての気づきは、「クワガタ幼虫は個体によって成長スピードが全然ちがう」です。
同じ種、しかも同じ親であっても1年で蛹になるもの、半年のもの、2年のもの、とバラツキが大きいです。
これを同じ飼育ケースで飼うのは非常に難しいですよね。
ちなみにカブトムシは、同じケースで飼っていればだいたい同じ時期に蛹になるよう、幼虫同士信号を送りあっているようです。
個別飼育用のクワガタ幼虫用ボトル
空ボトル
よって、このようなクワガタ幼虫用のボトルに幼虫を入れて飼育するのが一般的です。
800mlあれば、国産クワガタ幼虫ならばオスでもメスでも対応できます。
オオクワガタのオス幼虫は1500mlのボトルを使用したりしますが、コクワガタ・ノコギリクワガタ・ヒラタクワガタはそこまで大きくなくてもOKでしょう。大型のオスを狙う場合は是非大きいボトル使用下さい。
ボトルに入れる幼虫用マット
成虫の大きさにこだわりがなければ、幼虫用マットを入れるのが良いです。
(世の中には「成虫用」マットもあるのでお気をつけください!成虫用では幼虫は育ちません!)
本来クワガタ幼虫は木の中にいるので、ボトルに幼虫を入れる前に、マットを固く詰めてください。
おすすめはこちらのマット。カブトムシ幼虫にも使えますし、クワガタ幼虫ならほぼ何でもOKです。
マットは湿度が重要です。乾きすぎると生きていけません。自然界と同じです。
湿らせてギュッと握ったときに型崩れしない、かつ水がしたたらないレベルに水分調整してください。この範囲ならある程度適当でも大丈夫です。
水を入れすぎると戻すのが大変なので、少しずつ加水して状態を見て行ってください。
菌糸ビン
大きな成虫にしたい!なら菌糸ビンへ入れてあげてください。
マットより価格は張りますが、きのこの菌で朽ち木の環境を再現(いや超えているか)しているものです。大きくするには間違いない方法です。自然界のサイズを越えるような大きさも出るかもしれません。
クワガタ幼虫エサの交換頻度
基本的に3か月ごとに交換となります。
ただし、目で見てあまりにも劣化している、コバエが大量発生している、菌糸が泥状になっている、アオカビに全面覆われた、などの際は3か月を待たずに交換してください。
逆に3か月経っても菌糸がきれいなまま、であれば多少は交換を遅らせても良いと思います。ギネスを狙うのでなければある程度適当でも大丈夫です。
成虫になるタイミング
採集したときにどういう状態か、にもよりますが、早ければ2-3か月で、遅くとも1年で成虫に変化していくはずです。
(ノコギリクワガタなどは2年幼虫をやるパターンもありえます)
また、なるべく温かい環境で育てれば早く成虫になります。「累積温度」という考え方があり、暖かい環境ではすぐに累積温度が貯まりますが、低温環境ではなかなか累積されないため幼虫期間が延びます。
最後に!
いかがでしたでしょうか?
これでどういう公園の、どういう場所のどういう朽ち木を狙えばクワガタ幼虫が採れるか、そして飼育できるかお分かり頂けたのではないでしょうか!?
真冬であっても是非、次のお休みにでも挑戦されてはいかがでしょう。
吉報をお待ちしています!
***カブトムシ採集ならこちら!***
***昆虫採集ツアーならこちら!***


 https://kabukuwa.info/archives/3937
https://kabukuwa.info/archives/3937